こんにちは!インターン生のエバラです。
ご存知の方も多いと思いますが、今年は明治維新150周年です。
大河ドラマで西郷隆盛を取り上げるなど、盛り上がりをみせています。
明治と言えば、文明開化。
今までの鎖国をやめ、一気に西洋・欧米の文化が入ってきました。
そこでふと思ったのですが、西洋文化が入ってきたことで、明治時代の建築、屋根は変わったのでしょうか。
今回は、そんな明治時代の開国と屋根の関係について気になったので調べた結果をご紹介します。
まず、明治初期の都市の建築や住宅事情をご紹介していきます。
明治期の建築の大きな特徴は、和風の建物に、西洋風の要素が加えられたことです。
明治維新の少し前から、日本はペリー来航によって開国していました。
開国に伴って横浜や長崎、神戸などの外国人居留地に、「西洋館」が建てられました。
時代的には後のものですが、たとえば長崎のグラバー邸や、神戸の風見鶏の館などは今でも残っていますね
その初期の西洋館は、宅内の間取りは西洋風だった一方で、見た目は、和風と西洋風が混在したものだったのです(瓦屋根+ベランダなど)。
なぜそんなふうになったのかというと、居留地の西洋館は、日本人の大工が、外国人の設計図をもとにして、間取りとは無関係に日本家屋の伝統的な形式を用いて造ったからです。
また、開国した日本では、主に政府関係者が諸外国の賓客をもてなすための場所として、西洋風建築を必要としていました。
その需要から、接客施設としての洋館がどんどん建築されていきました。
そして西洋風建築が、上流階級のプライベートな住宅として建てられたのは1871(明治4)年のことでした。
このように明治初期から西洋風建築が輸入され、江戸時代の景観がなくなっていきます。
3.明治・大正の屋根事情:明治・東京、瓦屋根の定着
公的な建築物では、西洋化が進展していきました。
では、住宅はどうだったのでしょう。
ここでポイントになるのは「火事」です。
「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉が残るほど、江戸は火災の多い都市でした。
それを憂慮した明治新政府は江戸時代から続く火災対策として、1881(明治14)年に「甲27号」防火令を出しました。
内容は、東京の中心部の家屋を耐火改修させるというものです。
対象となった地域は、銀座、新橋周辺です。
ここは今でこそ東京の中心部の一つですが、未開発だった当時は街はずれだったのです。
屋根については、瓦葺きさえ少なく、杮(こけら)葺き(注1)の家が多いくらいでした。
現在の都会のイメージからは想像もできません。
しかし、銀座は横浜=外国へ通じる駅の一つ。
政府としては外国に見せても恥ずかしくないようにしないといけません。
つまり、外国にアピールするために、国の威信をかけて、銀座を開発しようとしたのです。
そのとき、選択肢として、れんが造・石造・土蔵造の三種類の建築が可能だったそうですが、多くの人々は西洋風のれんが造ではなく、伝統的な土蔵造を選びました。
当時の政府はれんが造を強引に推進していたため、住民はその反動で選ばなかったことが考えられます。
また、れんが家屋は、以前までの生活風習が変わってしまうので嫌われたそうです。
れんが造を推進する政府に反対して、自殺者がでるほどの抵抗でした。
こうして苦労を経た人々が選んだのは土蔵造。
その屋根は、もちろん瓦です(ようやく屋根の話に入れました)。
結果として、改修以前の板葺き・草葺きだったほとんどの家屋が、瓦葺きに代わりました。
1887(明治20)年に工事は完了し、当時の東京知事は「4万戸がことごとく瓦屋になった」と豪語しています。
逆に言えば、それまでの東京は木造板葺き・草葺きの町並だったということです。
以前の記事では、「幕府は、1720年に瓦屋根が許可し、以後防火対策として奨励していきました」と説明したのですが、政策に反して、民衆にはどうやらあまり定着しなかったようです。
というのも、幕府が許可したものには瓦の使用が許可・奨励されていたのですが、個人が勝手にすることは禁止だったのです。
むしろ、屋根に銅瓦など使おうものなら、「豪華すぎる」ということで奉行所に呼び出されていたそうです。
そして、明治になって、建築に対する制限が緩和されました。
個人が自分の意図を建築に取り入れる基盤ができつつあったのです。
伝統的な屋根=瓦屋根と連想してしまうかもしれませんが、瓦が庶民にとって馴染み深いものになるのは、明治以降のことだったのですね。
勝手なイメージで、江戸時代になったら全戸瓦屋根がフツーとぐらいに思っていたのですが、どうやらそこまでではなかったようです。
明治維新というのは、文字通り(?)東京を一新するような改革だったのですね。
当時の人々がどのような世界に住んでいたのか、少しでも伝わったならば幸いです。
(注1)杮(こけら)葺き:ヒノキやマキなどを薄くはいだ板。屋根を葺く際に用いられる。
参考:
内田青蔵(2016)、『日本の近代住宅』、鹿島出版会、pp.18~19
内田青蔵・大川三雄・藤谷陽悦(2008)、『新版図説・近代日本住宅史』鹿島出版会、pp.18~19
小沢朝江、水沼淑子(2006)、『日本住居史』吉川弘文館、pp.230 ~256
初田亨(1981)、『都市の明治 路上からの建築史』第二章、筑摩書房
・当社及び記事作成者は、当サイトに掲載されている記事や情報の内容に関しては十分な注意を払っておりますが、それらについての正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。
・当サイトに記載された情報のご利用については、ユーザー自身の責任において行われるものとし、ユーザーが当サイトから入手した情報に基づいて直接的または間接的に被ったいかなる損害について、当社および記事作成者は一切の責任を負いません。


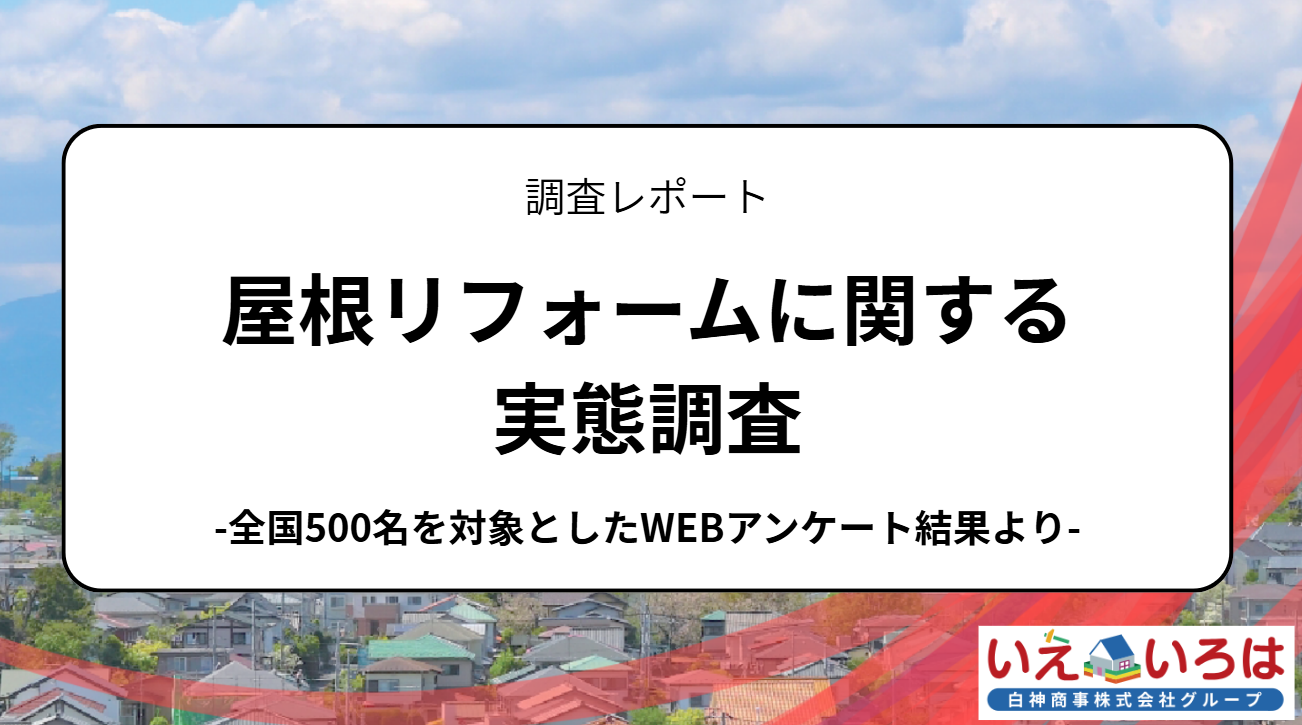







 屋根工事店をエリアで探す
屋根工事店をエリアで探す

