やねいろは運営会社へ連絡します
工事店名と工事店番号をお伝えください。
屋根材の種類
瓦(和瓦、平板瓦等)


- 長所
-
- 初期費用はかかるが、メンテナンス料があまりかからないため、長期的にリーズナブル
- 断熱性に優れている
- 耐火性能が高い
- 酸性雨や潮風等に強く、耐候性に優れている
- 色が非常に落ちにくい(釉薬瓦)
- 見た目の重厚感や趣がある(和瓦)
- 見た目がすっきりしている(平板)
- 見た目が明るい(マウント系)
- 短所
-
- 重いため、家の荷重が大きくなり、地震などの際は不利
- 価格が高い
材料
田畑や山の粘土が主原料です。有機物、粗砂、アルカリ分を含まないもので、水や風などで移動して一定の場所に堆積した成層粘土が多く使用されています。
粘土はけい酸やアルミナが主成分でFe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O3などを含んでいます。これらの成分は焼くと、化学変化をして硬い材料になります。
製法
粘土を繰り返し練り混ぜ硬練りとし、型に入れて圧縮成型機で成型します。成型された表面を磨いたのち、型から取り出して天日乾燥を行います。乾燥後は窯に入れ900~1500℃の高熱で焼き上げます。
表面に炭素の被膜を作ったいぶし瓦、酸化鉄・マンガンなどの釉薬を塗って焼いた釉薬瓦があります。
種類別の性質と形状
- いぶし瓦
- 表面に炭素(すす)の被膜を作った瓦です。油分によって水の浸透を防ぎます。
- 釉薬瓦(ゆうやくがわら)
- 瓦の表面に上薬(うわぐすり)を塗って焼き付けた瓦です。釉薬の種類によって、銀、黒、オレンジ、緑、青など着色されており、つやを出すものとつやを消しているものがあり、色は焼き付けのため、色褪せが非常にしにくいという特徴があります。また強度が大きく、防水性に富み、耐寒性もあります。
瓦の分類と大きさ
瓦の形状等はJISで規定されており、JISで制定する形状は和瓦とS瓦があります(JIS A 5208)。またJISで規定されてはいませんが、現在洋風の屋根によく使われる平板瓦、マウント系瓦も主流となっています。
1枚の瓦の大きさは3.3m2(1坪)当たりの面積に敷き並べる枚数によって決められます(和瓦53Aは3.3m2に53枚並べられ、平板40枚判は3.3m2に40枚並べられます)。
その他の瓦
- プレスセメント瓦
- プレスセメント瓦は、普通ポルトランド等のA・B種セメントを混合し、型に詰め、油圧機等で圧力を加え脱型後に養生してできた瓦である。完成後に色を着色することが多く、色褪せの観点から最近ではあまり使用されていない。
化粧スレート
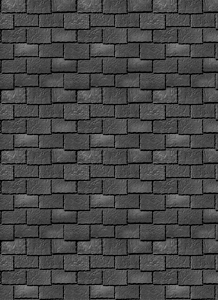

- 長所
-
- 初期コストは瓦より安い
- 軽量であるため災害に有利
- 短所
-
- 表面の塗膜で防水しているため、定期的に(10年毎が目安)に塗り直す必要がある
- 紫外線や雨などで色あせてくるため、年数が経つと見た目が悪くなる
- 通気性が悪い
- 断熱性が悪い
化粧スレートは塗装なので色持ちがやや劣りますが、安価で厚みがあります。
化粧スレート葺は、薄い定形の板を重ねて、並べたものです。横方向にすきまができるので、一段上の板とのずれ(葺き足)の2倍以上の奥行の板を用いて、すきまからの水を受けます。
金属屋根


- 長所
-
- 初期コストは瓦より安い
- 軽量である
- 見た目がシャープである。
- 雪が滑りやすく、すがもれが発生しにくい
- 緩めの勾配でも可能
- 短所
-
- 表面の塗膜で防水しているため、定期的に(10年毎が目安)に塗り直す必要がある
- 紫外線や雨などで色あせてくるため、年数が経つと見た目が悪くなる
- 通気性が悪い
- 断熱性が悪い
- 遮音性が悪い
金属屋根の特徴としては、まず軽いということがあげられます。屋根材が軽いことで、例えば屋根が受ける地震力が小さくなります。また、金属板は現場で端部を折り曲げて加工できるため、勾配を緩く葺くことが可能であり、特に長い材料(長尺材)を用いた葺き方では1寸勾配などにすることができます。
一方で欠点としては、塗装なので色持ちがやや劣ること、熱を伝えやすい(熱伝導率が大きいこと、雨音が聞こえやすい(遮音性に劣る)こと、屋根材料の一つ一つが大きいために風などで部分的に被害があった場合に比較的多くの部分を変えなければならないこと、熱膨張率が高い(材料の収縮が大きい)こと、金属材料のみでは結露が発生するので断熱性と防露性を持つ部材を金属材料に付加しなければならないことなどがあげられます。
また、金属板を屋外など水がかかるところに用いる場合は、違う金属同士が触れることは避けなければなりません。これは金属ごとにイオン化傾向(イオンのなりやすさ)があり、異なるイオン化傾向の金属同士が触れることで、一方の金属がもう一方の金属を腐蝕していくからです。
イオン化傾向の表は以下の通りです。
| K | Ca | Na | Mg | Al | Zn | Cr | Cd | Fe | Co | Ni | Sn | Pb | (H) | Cu | Hg | Ag | Pt | Au |
| →矢印の方向にしたがってイオン化しにくくなる→ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属板の材料としては、以下のものがあります。なお、ほとんどのものがコストの関係から鉄(鋼板)を主原料としています。
ガルバニウム鋼板
鋼板の表面に、アルミニウムと亜鉛のめっき(アルミニウム55%、亜鉛43%)を行ったものです。熱反射性、耐熱性などに優れるアルミニウムと、錆びの進行を防ぐ機能(防食機能)を持つ亜鉛で鋼板をめっきすることにより、通常の鋼板よりも優れた性能をもっています。また最近はガルバニウム鋼板の表面に着色された石粒を吹き付けた金属板(石付)などもあります。
トタン板
鋼板の表面に、亜鉛のめっきを行ったものです。水に触れたときに、先に亜鉛が溶ける性質を持つことから、鉄が溶けることを防ぎ、鉄の錆び(腐食)も防いでくれます。トタン板は過去には屋根材として使用されていましたが、現在の金属屋根としては、ガルバニウム鋼板が多く使われています。
ブリキ板
鋼板の表面に、すずのめっきを行ったものです。水に触れたときに、すずは鉄よりも溶けにくいため(鉄が溶け出すため)、缶飲料や缶詰の材料として使用されます。
ステンレス板
鉄を50%、クロムを10.5%以上含む合金であり、クロムが空気と結合してできた皮膜により、錆びにくい性質を持ちます。強度も強く、優れた性能をもちますが、価格はガルバニウム鋼板よりも高くなります。
銅板
言葉の通り、銅で構成された金属板であり、銅は空気中で酸化するため、褐色から緑青色へ変化していきます。耐久性に優れ、昔から神社仏閣などで使用されていますが、価格が高いため、一般住宅ではあまり使われません。
人工スレート(波型)


- 長所
-
- 初期コストが安い。
- 軽量であるため災害に有利。
- 短所
-
- 表面の塗膜で防水しているため、定期的に(10年毎が目安)に塗り直す必要がある。
- 紫外線や雨などで色あせてくるため、年数が経つと見た目が悪くなる。
- 通気性が悪い
- 断熱性が悪い
形状としては、波の深さ(谷の深さと言います)が15mm以上の小波板、25mm以上の中波板、35mm以上の大波板の3種類が制定されています。 屋根材として使われることが多いものの、形状としてあまり美的ではないことから、住宅などの屋根に用いられることは少なく、工場など形状へのこだわりが比較的薄い建築物に使用されます。小波板は一般屋根材や外壁材として、中波板は一般屋根材として、そして最もよく見る大波板は工場などの屋根材として使われることが多いです。
人工スレート(波型)の葺き方は、化粧スレートの葺き方と同じく、薄い定形の板を重ねて、並べます。


 屋根工事店をエリアで探す
屋根工事店をエリアで探す

